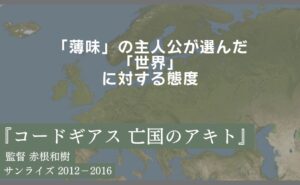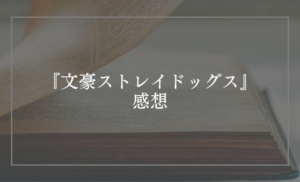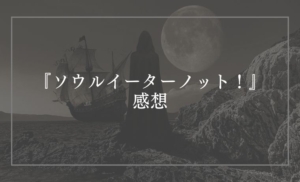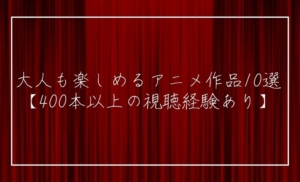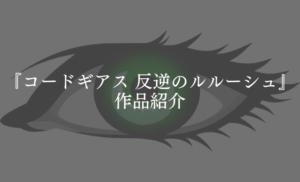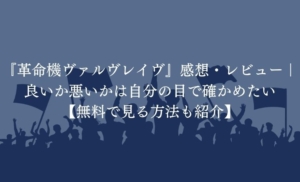※タップすると楽天のサイトに移動します。
| 放送 | 2014年 |
| 話数 | 全13話 |
| 制作 | アームス |
| 原作 | 岡本倫(週刊ヤングジャンプ) |
| 監督 | 今泉賢一 |
| シリーズ構成 | 北島行徳 |
| キャスト | 逢坂良太、種田梨沙、洲崎綾、M・A・O |
『極黒のブリュンヒルデ』の視聴動機となったのは、原作者が『エルフェンリート』と同じだからです。
『エルフェンリート』はなかなかに衝撃的で、刺激の強い作品でした。
まったく同じものを『極黒のブリュンヒルデ』に期待していたわけではないのですが、残虐さやダークな部分、SF要素などは『エルフェンリート』と似通っていたと思います。
アニメ化されたのは原作の途中までで、一部設定に変更もあったようですけどね。
本記事では、2014年に放送されたアニメ『極黒のブリュンヒルデ』について綴っていきます。
『極黒のブリュンヒルデ』感想1:「死」の影が常にちらつく物語
刺客に狙われ続ける寧子たち
『極黒のブリュンヒルデ』で一番に感じたのは、「死」の影が常にちらついている物語であるという点です。
その要因の一つとなっているのが、黒羽寧子や橘佳奈たちが「研究所」から脱走した「魔法使い」であり、「研究所」からの刺客に命を狙われている、というところですね。
魔法使いたちの能力はどれも普通の人間をはるかに凌駕しており、しかも寧子たちを狙う刺客は全員がAクラス以上。
その能力も、
- 近くにあるものは何でも切り刻むことができる
- 口からビームを放出する
など、一撃で相手の命を奪うことができるものが多く含まれています。
これに対抗する寧子たちの能力はBクラス以下であり、しかも寧子以外の能力は直接的な戦闘できるものではないため、まともに戦っても到底勝ち目はありません。
そのため、刺客に発見されることがそのまま死に直結するような緊張感があるのですね。
刺客の脅威は最後まで付きまといますから、これが『極黒のブリュンヒルデ』という作品に強く「死」を意識させる理由になっていると思います。
「鎮死剤」問題
寧子たちを追う刺客の存在は、確かに脅威です。
ただ、これだけだと似たような設定の作品は他にいくらでもありますよね。
『極黒のブリュンヒルデ』が数多ある他の作品と違うのは、やはり
魔法使いたちはその生命を維持するために、毎日鎮死剤を服用する必要がある
という点なんだろうと思います。
これがあることで、寧子たちの「死」がぐっと身近に迫ってきます。
さらに、寧子たちは研究所を脱走してきているため、鎮死剤のストックには限りがあるんですよね。
普通の人間が刺客に追われているだけなら、息をひそめて身を隠していれば何とかなるかもしれません。
でも、寧子たちの場合、それで待っているのは鎮死剤の枯渇による死なのですね。
そのため、危険を承知で鎮死剤入手のための行動を起こす必要があります。
座して死を待つより、身を危険にさらしてでも活路を開こう、というような切迫感ですね。
物語序盤、第4話までに描かれていたのがまさにこの話でした。
ただ、第4話で確保できた鎮死剤の量は限定的なものであり、新たに入手することもできなくなってしまったため、この「鎮死剤問題」は解消せず、その後もずっと物語に滞留し続けることになります。
この鎮死剤の存在は、『極黒のブリュンヒルデ』という作品の雰囲気にとても大きな影響を与えていると思います。
「イジェクトボタン」の存在
魔法使いたちのハーネストに付属したイジェクトボタンは、「死」そのものというより「(魔法使いたちの)命の軽さ」を象徴していると言った方が正しいのかもしれません。
ボタン一つで、手軽に奪えてしまう魔法使いたちの命。
これについては、寧子たちばかりでなく刺客となる魔法使いたちも変わりがありません。
「身体が溶けて死んでいく」という凄惨さの方に目が向きがちなイジェクトボタンですが、この「簡単さ」も死をごく近いものとして感じさせる特徴の一つとなっているようと感じました。
『極黒のブリュンヒルデ』感想2:コミカルさと、その根底にあるもの
カズミの役割
寧子たち魔法使いの過酷な運命に目が向きがちな、『極黒のブリュンヒルデ』。
でも、悲壮感たっぷりの作品かというとそういうわけでもないのですね。
コミカルな要素も少なからずありました。
そのあたりを主に担っていたのが、カズミ=シュリーレンツァウアーだったかな、と思います。
関西弁で、下ネタを多く口にし、そのくせ胸が小さいことを村上からいじられる、といった個性が、作品を弛緩させるのに効果的でした。
他の魔法使いたちにはない、村上に対する積極性も、作品に変化を与えていたと思います。
根底にあるのは達観
カズミ以外にも、
- ツッコミが辛辣な村上
- 自作の鼻歌を歌いながら洗濯物を干している寧子
- 天然ボケで食べ物への執着が強い小鳥
など、作品に「ゆるめの雰囲気」を作り出す要素があちこちに挟まれていました。
ただ、こうしたコミカルな要素が一時的な息抜きでしかなかったのもまた事実でした。
寧子たちに課された運命は、笑いで吹き飛ばせるようなものではないですからね。
新たな鎮死剤の供給はなく、今ある分が底を突けば待っているのは確実な「死」。
でも、彼女たちはそうした自らの運命を受け容れているようにも見えるんですよね。
カズミをはじめとする魔法使いたちの「明るさ」も、根底にはそうした「達観めいたもの」があるように感じました。
そこがまた、彼女たちの哀しさを大きくさせていたと思います。
『極黒のブリュンヒルデ』感想3:終盤は駆け足気味
急展開とその弊害
『極黒のブリュンヒルデ』でもったいなかったな、と思ったのは、終盤が駆け足になってしまった点です。
話数が足りなかったのか、展開が急で、描き方もかなり粗くなっていました。
ヘクセンヤクトは、その被害者と言ってもいいかもしれません。
最終盤の12話での登場は唐突でしたが、能力的にはもっと活躍できそうだし、重要な役割を与えられそうに見えました。
ところが実際には、大した活躍の場も与えられず、深く描かれることもなし。
「魔女の正体を明かす」という役割こそ担っていましたが、それを果たすために、申し訳程度に登場させたようにしか見えませんでした。
盛り込みすぎな終盤
物語が急加速を始めたのは、第11話で初菜が登場したあたりからだったと思います。
『極黒のブリュンヒルデ』は全13話の作品ですから、残り3話でこれだけの要素が盛り込まれていました。
- 魔女の真実
- ドラシルとグラーネ
- 小鳥の正体
- 九(いちじく)の目的
- 寧子と真子の関係
- 佳奈の秘密
- 寧子の本当の力
謎の多い物語なので、それを何とかまとめようとするとこうなってしまうのは仕方ないのかもしれません。
ただ、結局すべての謎は明らかになっていないんですよね。
そのあたりを知りたければ、原作を読むしかないのかもしれません。
原作をそのままアニメ化しようとするなら、無理矢理1クールに押し込もうとしない方が良かったように思いました。
寧子やカズミといったキャラクターはそれなりに魅力的でしたし、設定や謎も興味を惹かれるものだっただけに、もったいなかったと思います。
『極黒のブリュンヒルデ』感想:まとめ
終盤の駆け足と盛り込みすぎもあり、『エルフェンリート』ほどのインパクトは残念ながらなかったと思います。
ただ、まったくダメだったかというとそんなことはなく、登場人物たちの個性や描き方は悪くなかったですし、魔法使いの謎も興味を引くものになっていました。
アニメで描き切れなかった部分を、原作で読んでみたいという気分にはさせられましたね。
それと、
- 包帯だらけで登校してくる寧子
- 「人類補完計画」まがいの九の野望
- ゲンドウとレイを思わせる九と真子
あたりに、『新世紀エヴァンゲリオン』の影響(オマージュ?)を強く感じました。
今回は、以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。