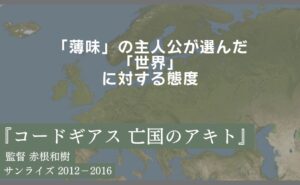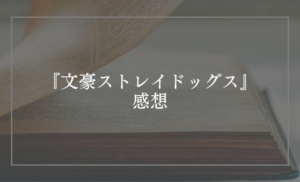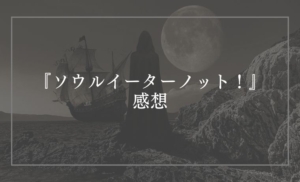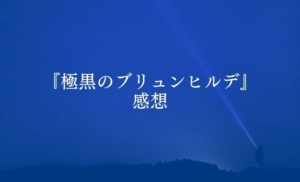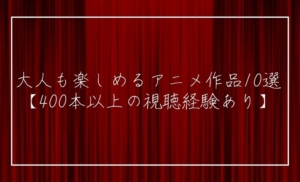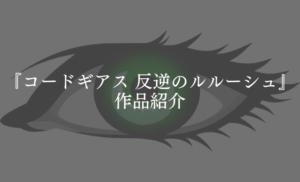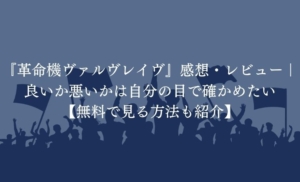※タップすると楽天のサイトに移動します。
| 放送 | 2014年 |
| 話数 | 全12話 |
| 制作 | アームス |
| 監督 | 梅津泰臣 |
| シリーズ構成 | 梅津泰臣 |
| キャラクターデザイン | 梅津泰臣 |
| キャスト | 田辺留依、真堂圭、東地宏樹、荒川美穂 |
梅津泰臣監督の作品で見たことがあるのは、
- 『MEZZO』(2004年)
- 『ガリレイドンナ』(2013年)
くらいなのですが、本作『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』がどちらに近いかと問われたら、これはもうわかりやすく『MEZZO』だったと思います。
- 特徴的な目元
- 丸みを感じさせるデザイン
- 性的な想像を喚起するカットの多用
といった女性キャラクターの描き方や扱い方に似たものを感じました。
第6話では、『MEZZO』の主人公鈴木海空来のコスプレをした人物もちらりと登場したりしていましたね。
ただ、物語そのものは『MEZZO』とはだいぶ違っていました。
というわけで本記事では、『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』について綴っていきます。
人間と魔術使い
人間と魔術使いは別の存在
『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』で一つ特徴的だと感じたのは、
人間と魔術使いは別の存在である
という考え方が根底にある点です。
「別の存在」と言っても、魔術使いが人間扱いされていないとか、魔術使いには人権がないというわけではありません。
そこまで極端に表面化してはいないのですが、といって魔術使い=魔術が使える人間という理解でOKか、というと、それも少し違っているように思えるのです。
「魔術を使える」ということが、優れた知性や卓越した運動能力と同じような「人間の持つ秀でた才能の一つ」ではなく、「人間ではない存在が持つ能力」と扱われている
とでも書けばいいでしょうか。
「魔術を使える」という事実によって、「人間」と魔術使いを分けているように見えるのですね。
魔術使いを受け入れるための魔禁法
魔禁法は『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』で最も特徴的な設定ですが、この法律の存在も「人間」と魔術使いが別鋳物であるということを暗に示しているように思えます。
というのも、法律によって魔術を縛ることを目的としている魔禁法は、
魔術使いを「人間」社会に受け入れるための装置
でもあるからです。
魔術を使えない「人間」にとって、野放しの魔術使いは脅威でしかないですからね。
魔術使いを排除するのではなく受け容れるには、魔術に制限を設ける必要があります。
その縛りとなるのが魔禁法です。
魔禁法は作品の中でも描かれている通り魔術使いにとって不便極まりない法律なのですが、これがあることで初めて、魔術使いは「人間」との共存が許されるとも言えます。
ただ、裏を返すとこれは、魔術使いと「人間」は明確に違う存在だ、と言っていることにもなりますよね。
魔禁法に見る魔術使いへの意識
さらに魔禁法からは、特にその運用面において「人間」から見た魔術使いへの意識が透けて見えます。
- 「魔法廷」という特別法廷が設置
- 弁護士ではなく「弁魔士」が弁護
- 一審制
特徴的なのは、このあたりでしょうか。
弁魔士の役割は弁護士とほぼ同じです(少なくとも作品中ではそう見えました)が、それ以外は民法や刑法などで裁かれる一般の裁判とは違っています。
特に、一審制というところは目を引きますね。
魔禁法が魔術使いにだけ適用される法律であるという点を考え合わせると、
「人間」は魔術使いを、全面的な好意を持って受け入れているわけではないらしい
ということが見えてくると思います。
そしてこの魔術使いに対する態度は、もっとわかりやすい形で現れたりもしています。
魔術使いに向けられる目
『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』という作品において魔術を使えるということは、必ずしもポジティブな要素にはなっていません。
魔術使いが、差別の対象になることもあるからです。
「異質なものを排除したい」というのは、他の多くの差別意識にも表れる人間心理の負の側面ですが、本作では魔術使いに対してそれが向けられているのですね。
そして、それを助長しているのが魔禁法が暗黙の裡に裏付けてしまっている、
「人間」と魔術使いは別の存在である
という考え方であるようにも思えます。
魔術が「人間の持つ(秀でた)才能の一つ」という位置づけであれば、魔術使いに対する差別意識というものは存在すらしないでしょう。
でも、『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』の世界ではそうではありません。
魔術使いがウドという蔑称の色が濃い単語で呼ばれることからもそれはわかりますし、第1話と第2話で描かれた銀行強盗のエピソードでは、セシルが弁護した小日向が、魔術使いであることを理由に職場で差別を受けていました。
マカルとラボネ
一方で、魔術使いサイドも「人間」に対する立場の違いから、2つの派閥に分かれています。
- 「人間」を憎み、対立的なマカル
- 「人間」に融和的で、共存を望むラボネ
マカルの陰謀が『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』という物語の核になっているわけですが、それはさておきここで注目しておきたいのは、
魔術使いたち自身も、自分たちを「人間」とは別の存在と考えている
という点です。
「『人間』に対する立場の違い」が前提になっているということは、暗に自分たちを人間ではない存在と位置付けているということになりますからね。
ラボネですら、その主張は「魔術使いも人間と認めてほしい」というものではありません。
つまり「『人間』と魔術使いは別物である」という考え方は、
人間たちが一方的に決めつけているのではなく、魔術使いたちも認めている
ということになります。
当然ながら、違いを認めることと差別を許容することは別です。
ただ、この魔術使い側の認識からも『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』の世界では、「人間」と魔術使いが別の存在であるという考え方が当たり前のものになっているということがよくわかります。
複数のジャンルが入り乱れる『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』

※タップすると楽天のサイトに移動します。
魔術と法廷以外の要素も?
『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』を見ていてもう1つ特徴的だと感じたのは、複数のジャンルが盛り込まれている点です。
- 魔術(魔法)もの
- 法廷もの
というあたりは、タイトルから予想がついたのですが、ディアボロイドの登場が「それだけではない」という印象を与えてくるんですよね。
主人公セシルが使う魔術がまさにこれ(ディアボロイドを作り出す金属魔法)で、
魔術で作り出したディアボロイドに戦わせる
というのが戦闘スタイルなのですが、結局戦うのはディアボロイドです。
そのせいで、セシルが魔術を使うたびに、
「これは果たして純粋な魔法ものと呼んでいいのだろうか?」
という違和感が心のどこかに生じていました。
それに拍車をかけるのが、第8話で発生するディアボロイド同士の戦いです。
ディアボロイドの直線的なデザインも関係していると思うのですが、その見事なバトルシーンはどう見てもロボットバトルでした。
タイトルから想像される「魔術もの」と「法廷もの」に加えて「ロボットもの」の要素も混じっているのが、『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』という作品だったようです。
「弁魔士ならでは」の要素は?
『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』にロボットものの要素を(わずかにとはいえ)感じたのは確かです。
とはいえ、それがメインになることはありません。
前面に出ているのはやはり「法廷もの」です。
「弁魔士」という耳慣れない単語を作り出し、それをタイトルにしているくらいですからね。
その点については、揺らぎはなかったと思います。
ただ、ちょっと物足りなかったのは「弁魔士なら」ではの悩み、みたいなものが描かれていなかった点でした。
わざわざ「弁護士」と「弁魔士」を分けたくらいですから、そういう話もあるのかなと勝手に期待はしていたんですけどね。
第4話で、
「どう見ても悪人という相手を、弁護しなければならない」
というセシルの葛藤が描かれてはいたのですが、これは弁護士にもありそうな話で、弁魔士特有とは思えませんでした。
『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』感想:まとめ
『ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル』で特徴的だと感じたのは、「魔術を使える」ということが必ずしもポジティブに捕らえられていないという点です。
「魔術を使える」というのは人と違った便利な才能ですし、使えない人にとってはあこがれの対象になってもよさそうですけどね。
自分ならやはり羨望の方が強くなりそうなので、その部分についてはうまく共感することができませんでした。
今回は、以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。