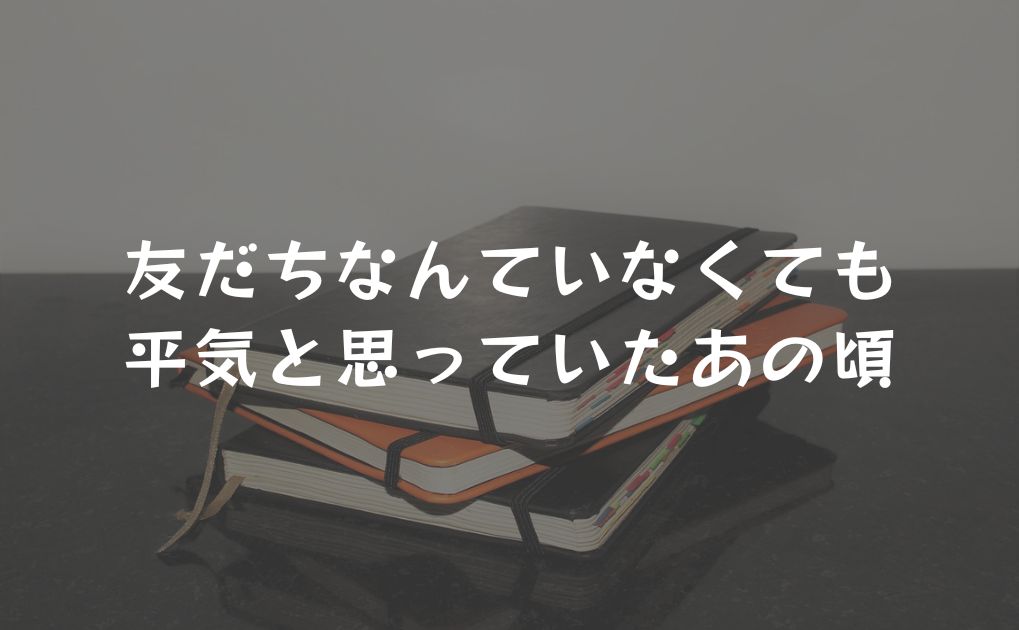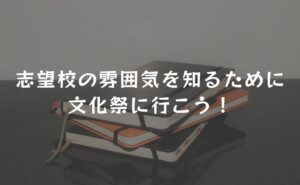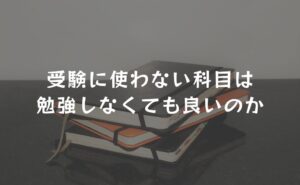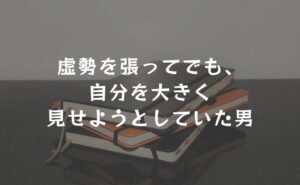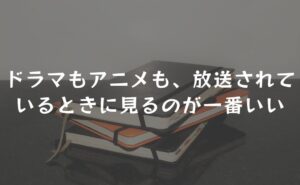僕は昔から、孤独には強い。
学生時代にありがちな、クラス替えや進学のときの「友だちできるかな、できなかったらどうしよう」という心配も、一度もしたことがない。
できないならできないで、別に構わないと思っていたからである。
「友だちなんていなくても授業は受けられるし、休み時間は自分の席で本でも読んでいればいい」と思っていた。幸運なことに、僕は当時から読書が好きだったから、一人で本を読んでいる時間はまったく苦痛ではなかった。「友だちがいないことで読書の時間が確保できるなら、むしろウェルカムだ」と考えていたくらいである。
一人で昼食を食べることにも、まったく抵抗はなかった。
最近の学生には、「便所飯」なる行為を敢行している人たちもいると聞く。僕にはちっともわからない感覚である。
一人で飯食って、何がいけないのだ。『孤独のグルメ』の井之頭五郎だって、いつも一人で飯を食べている。誰が何を言おうと、知ったことじゃない。堂々としていればいいのだ。
と、偉そうに孤独を語ってみたものの、では実際に学生時代の僕が、鋼鉄の精神と目を疑うような鈍感さでもって孤独を貫いていたのかというと、そうでもなかったりする。
友人は、いた。
中学時代も、高校生になってからも、大学に入学してからも一人になったことはなかった。「別に友だちなんてできなくても構わんのだけどな」の精神を高々と掲げ、友人を獲得するために何の努力もしてこなかった僕だが、友だちはきちんといたのである。
こんな風に書くと、僕が「何もしなくても人が寄ってくる、特別な存在」であるかのように感じられるかもしれない。でもまあもちろん、そうではない。
僕が学生時代孤独に陥らなかったのは、この面倒なひねくれ者にも「歩み寄ってやろう」と考える奇特な人たちがいたからである。僕に近づいたところで何のメリットもないと思うのだが、彼らは僕を陰で嘲ったり、見えないふりをしたりすることはなかった。一人でぽつんと座っている僕に声を掛け、一緒に話をし、同じ時間を過ごしてくれたのである。
もしそこに特別な何かがあったのだとしたら、それは彼らの中にこそ、存在していたのだろうと思う。
そうして僕と仲良くしてくれた友人たちの一人に、大畑くん(仮)がいた。
大畑くんとは、高校三年間クラスが同じだった。しかし、では高校時代の一番の親友だったか、というとそうでもなかった。在学中、僕と大畑くんが言葉を交わしたの回数は、片手で数えられるくらいだったんじゃないかと思う。
そんな僕たちが急接近したのは、高校卒業後に予備校で再会したことがきっかけだった。その年の大学受験で共に見事な玉砕を遂げていた僕と大畑くんは、春から同じ予備校に通うことになったのである。
そこでまた、僕たちは同じクラスになった。クラスには他に同じ高校の出身者がいなかったため、大畑くんとは自然と話をする機会が多くなった。
大畑くんと仲良くなったのには、「サッカー観戦」という共通の趣味を持っていることが判明したのも大きかった。どちらもJリーグをよく見ていて、同じ地元チームのファンでもある点も同じだったのである。浪人生のくせに勉強をさぼって、一緒にスタジアムまで試合を見に行ったこともあった。ひいきチームが負けてしまった試合なのだが、何だかすごく楽しかったのを覚えている。
受験を終えて、大畑くんと僕は別々の大学に進学することになった。それでも、二人のつながりは途切れることなく続いた。これは、僕にとってはとても珍しいことだった。「学生時代、孤独ではなかった」とは書いたものの、それはあくまで在学中に限った話だったからである。ほぼすべての友人関係が、卒業と同時にぷっつりと途切れた。それが僕にとっての当たり前だった。
しかし大畑くんは、違っていた。大学時代に留まらず、就職してからもその関係が続いたのである。
彼が僕にとってヴェルタースオリジナルばりに特別な存在となったのは、やはりサッカーの存在が大きい。僕たちの間で交わされる会話のほとんどが、サッカーの話題だったからだ。休みの日に会う約束をしたのも、サッカーを見に行くためだった。平日夜に開催される試合のために、会社帰りに待ち合わせをして一緒にスタジアムに行ったこともあった。
正月から一緒にサッカー観戦していた時期もある。天皇杯の決勝が、まだ元日に開催されていた頃だ。初めて見に行ったのは、応援しているチームが決勝に進出した年だった。そこで経験した「一月一日からスタジアムでサッカーを見ている」という特別感が楽しくて、次の年からはひいきチームの勝ち残りに関係なく、今はなくなってしまった旧国立競技場まで二人で足を運んだ。
正確な回数は覚えていないが、おそらく四、五年連続でやっていたんじゃないかと思う。
そんな大畑くんとのつながりも、今ではまったくなくなってしまった。
最後に会ったのは、もう思い出せないくらい昔になってしまっている。
大畑くんとの関係に亀裂が走る、特別な何かがあったわけではない。ケンカをしたわけでもないし、手ひどい裏切りを受けたなんてこともない。どちらかがとんでもなく遠くに転勤になってしまったとか、いきなりライバルチームのサポーターに転向してしまった、とかでもない。
何となく連絡を取らずにいたら、その期間が思いのほか伸びてしまったというだけのことである。ただ、この「何となく」が意外と重かった。空白期間が長くなればなるほど、連絡を取ろうという気持ちは起こらなくなってしまうものだからである。
それは、過去にどんなに親しくしていた相手であっても変わらないらしい。
今振り返って思うのは、「二人の恒例行事」みたいなものを作っておけばよかった、ということだ。春と秋には一緒にサッカーを見に行くとか、年末には一度顔を合わせる機会を設けるとか、直接会うのは難しくても、半年に一回は連絡を取り合うようにするとかの、「ちょっと面倒だけど、定期的にやるようにしていること」を決めておけば、今でも大畑くんとの付き合いは続いていたんじゃないかと思う。
何もしなければ、人との関係は途切れてしまう。つながりを維持するためには、それなりの努力が必要なのだ。
そして、一度途切れてしまった関係はそう簡単には元に戻せないらしい。
孤独に強すぎたせいで、そんな当たり前のことも僕はわかっていなかった。その無知を、今はほんの少しだけ恨めしく思っている。