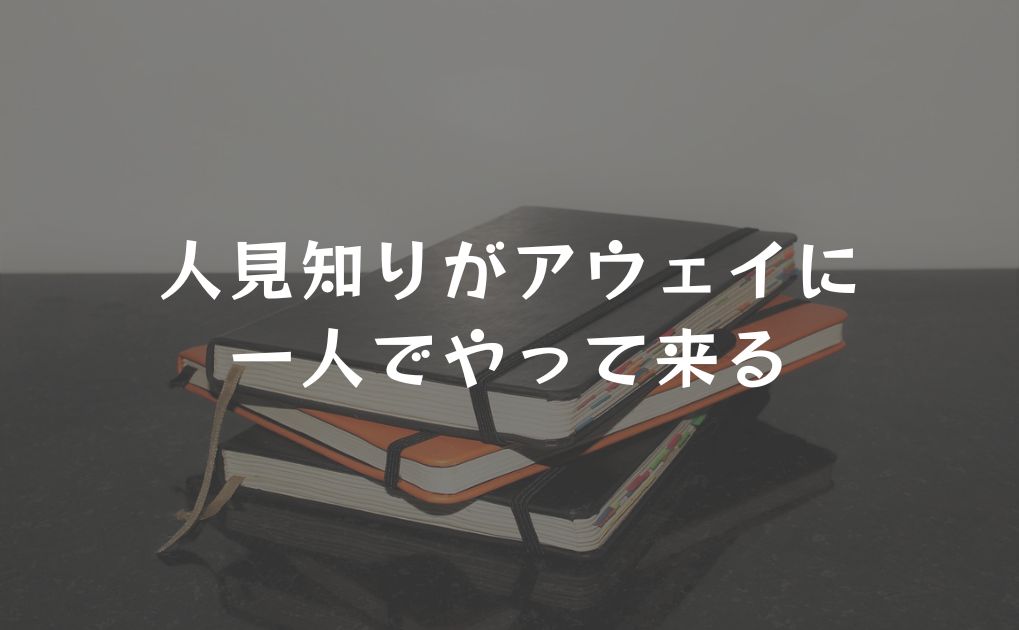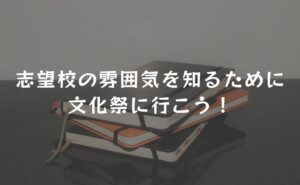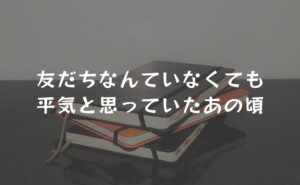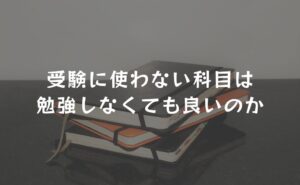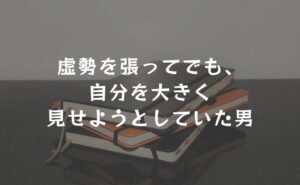人見知りは、実に厄介な性質である。
知っている人たちが相手なら、明るく楽しく、いくらでも話をすることができる。でも、そこにあまり仲良くない人や知らない人がやってくると、途端に委縮してしまう。顔が強張り、口数が極端に減り、モジモジと身を捩らせながら一刻も早くこの状況が終わってほしい、という願いで頭がいっぱいになってしまう。
よく知らない人には近づかないでほしいし、それでもやってきてしまうならすぐにどこかに行ってほしい。 そんな排他的な思考を、常に心に留めているのが人見知りなのだ。
ちょっと前に見た『いなり、こんこん、恋いろは』という2014年放送のアニメにも、そんな人見知り諸氏を大きくうなづかせるエピソードがあった。作品のちょうど真ん中に当たる、第5話である。
この作品は、神の力の一部を授かったことにより、他人に変身できる神通力を手に入れた女子中学生の物語だ。その変身能力をきっかけに、主人公の伏見いなりはクラスメートの美少女・墨染朱美と親しくなる。
一方いなりには、墨染と懇意になる前から仲良くしている女子がいる。三条京子と、丸太町ちかの二人だ。元々は、いなり、三条、丸太町の三人が仲良しグループだった。そこにいなりが連れてきた墨染が加わることでひと悶着起こる、というのが第5話である。
火種となったのは、おさげにメガネ、小太りでオタクの丸太町だ。既に数え役満といった様相を呈しているが、これらに加えて人見知りも備えているのだから、圧巻の充実ぶりである。
彼女は墨染のことはよく知らない。しかし、才色兼備で学校の人気者でもある墨染が、自分と対極の存在であることはわかっている。
そんな丸太町はもちろん、墨染の加入を喜ばしく思っていない。墨染を連れてきたいなりにも、ちょっと腹を立てている。彼女にとって、いなり、三条、自分の仲良し三人組は居心地のいい場所だった。それを乱されたことが、気に入らないのだ。墨染のいないところで、「三人のままが良かった!」とまで言い放つ始末である。
実に、典型的な人見知りである。
これで墨染が歪んだ性格で、自分と真逆の丸太町を小馬鹿にしている、とかであれば、気の毒な丸太町への同情心も湧いただろう。しかし実際の墨染は大変性格が良く、丸太町に避けられていることにも気付いていて、それに思い悩んでいるくらいなのである。
こうなるともう、丸太町には立つ瀬がない。完敗である。
本当にツラいのはアウェイ
ただ、実はこの「外からやってくる異邦人パターン」は、人見知りにとってまだ最悪の状況ではなかったりもする。こちらのホームグラウンドに、相手がやってきている状態だからだ。
仲間が周りにたくさんいるのである。
ツラいのは、この逆だ。「仲良しグループの中に、突如異邦人として放り込まれた人見知り」のケースである。
このケースを考えるとき、いつも思い出す話がある。高校の同級生の、結婚式に呼ばれたときのことだ。
僕が座った六人掛けの円卓に、見知らぬ顔があった。
そのこと自体は、特に珍しいことだとも思わなかった。友人の結婚式で、初対面の人と同じテーブルになったことは、過去にもあったからである。
問題は、彼が1人で来ていたことだった。これはちょっと、他では記憶にない。初対面の人と同席することになった場合でも、相手は2人以上のグループで来ていることが普通だったからである。
ところがそのテーブルでは、僕を含めた他の5人全員が、彼と初対面だった。
席次表を確認すると、彼のところには「新郎 中学同級生」と印刷されていた。他に「新郎 中学同級生」はいなかったから、どうやら本当に1人だけ呼ばれたらしい。数合わせで、我々「新郎 高校同級生」のテーブルに放り込まれたのだろう。何とも雑な扱いである。
しかし、この状況はツラい。僕が彼の立場なら、席次を見た瞬間あらゆる手段を駆使してその場から撤退している。
新郎の方も、よく1人だけ呼ぼうと思ったものだ。せめてもう一人、彼の知っている「新郎 中学同級生」を呼んであげようという心は働かなかったのだろうか。それとも彼は、ごく稀に出現する「コミュ力おばけ」で、アウェイに1人で乗り込んでも無双できるコミュニケーション界のクリスティアーノ・ロナウド的な存在だったりするのだろうか。
そんな好奇の目でしばらく彼の様子を眺めていたものの、クリロナの片鱗は少しも見られなかった。むしろ実際はその真逆で、人見知りなのではないかという疑いが湧いてきてしまったくらいだ。
口を真一文字に結んで卓上の皿に目を落としている時間が、とにかく長い。隣の席の同級生が気を使って声を掛けても、一言二言返すだけですぐに黙ってしまう。
間違いない、彼は人見知りだ。
途中で僕はそう確信したのだが、それならそれで、すごい話だとも思った。「自分以外が全員知り合い」のこの完全アウェイ状態は、人見知りにとって最もツラい状況のはずだからだ。それが3時間近く続く上に、途中離脱もできないのである。僕なら想像しただけで干上がってしまいそうだ。
そんな苦行を覚悟してまで、よくも式への出席を決断したものだと思う。それとも彼は新郎とはよほど親しい関係で、この地獄に耐えてでも、親友の結婚を祝いたかった、とかなのだろうか。
そんなこんなであれこれ想像を巡らせたりしていたのだが、実はそれも、最初の頃だけだったりする。時間が経つにつれて彼の存在にも慣れて、まったく気にならなくなってしまっていた。式の余興もあったし、アルコールが入っていたのもあるし、同じテーブルに座っている彼以外の4人とは久しぶりの再会だったこともある。
気が付くと、彼は卓上の空気のような存在になっていた。
もしあの話題が出なければ、そのまま忘れ去られていただろうと思う。
突然の覚醒
異変が起こったのは、話題が新郎の部活動に及んだときだった。
高校時代、新郎は地学研究部に入っていた。地学に特別興味があったから、というわけでは全然ない。僕たちの通っていた高校では「全生徒に部活動の加入を義務付ける」という、誰のためなのかよくわからないルールがあって、それに従う形で籍だけ置いていたのである。
地学研究部は非常にゆるく、活動も、しているのだかしていないのだかわからないような部だった。そのため新郎のように、「特にやりたいことはないんだけど、どこかの部活に入らないといけない」という生徒たちの隠れ蓑になっていたのである。幽霊部員が、異常に多かったらしい。3年生のとき、部長を押し付けられたクラスメートが「部員が把握しきれない」と嘆いていたのを覚えている。
そんな新郎だが、中学時代は野球部のレギュラー捕手だったらしい。怪我さえなければ、高校でも野球を続けていたのだそうだ。
新郎の口からたびたび聞かされたその話を同級生の一人が口にしたとき、それまで黙って話を聞くだけだった「新郎 中学同級生」が、「は?」と素っ頓狂な声を上げた。
我々は、びっくりしてそちらを振り返った。
「は? 野球部のレギュラー? あいつがですか?」
アルコールの影響で顔を赤くした彼は、これ以上ないくらい目を見開いていた。
「……うん、キャッチャーのレギュラーだったって聞いてるよ」
突然のことに身を固まらせた我々の中から、いち早く我に返った同級生の一人が答えを返す。
すると彼は眉間にしわを寄せ、「それ、誰が言ってました? 本人ですか?」とさらに問いを重ねた。
「そうだね、自分で言ってたよ。おれらの学年に、あいつと同じ中学出身の奴いなかったしね」
「そうですか。自分で。高校ではそんなこと言ってたんですね、あいつ」
「なになになに。何か違ってるの?」一つ席を挟んだ右隣の同級生が、身を乗り出してたずねる。何かを想像しているようで、その顔は期待に輝いている。
「もしかして、レギュラーじゃなかったとか?」
「ええ、まあレギュラーじゃなかったのは間違いないですね」と彼はうなづいた。「違うのはそれだけじゃないですけど」
「それだけじゃない?」
「ええ。そもそも野球部じゃないんですからね、あいつ」
「え?」
素っ頓狂な声を、今度はこちらが上げる番だった。
「そうなの?」
「はい。一瞬、野球部員だったことはありますけど、基本は野球部じゃないですね」
「んんんん? 一瞬? 何それ。どういうこと?」
「新郎 中学同級生」によると、一応新郎は、中学校入学直後に野球部に入部はしているらしい。ただ、ゴールデンウイーク明けから練習に来なくなったのだそうだ。そのままの状態が一学期末まで続き、終業式の日に退部になったという話だった。
すなわち、彼の野球部員としての実稼働期間は1ヶ月弱で、1年生の夏休み前には退部していたということになる。
「なるほど、それなら確かに一瞬だ」と席にいた我々全員が、彼の言葉に納得してうなづく。
新郎が野球部をやめた理由は、彼もよく知らないらしい。ただどうやら、怪我が理由ではないそうだ。
となると、新郎が我々に伝えていた中学時代の部活歴は、ほぼすべてが嘘で塗り固められたものだった、ということになる。
我々は、俄然色めきだった。これは重大な裏切りである。彼は自分の結婚式に呼ぶほど親しい友人である我々にまで、嘘を吐いていた自らの経歴を飾っていたのだ。これは信義に背く行為と言っていい。我々は断固抗議する。そんなことする奴はもう友だちじゃないから、さっき渡したご祝儀の3万円も返してほしい。
……と、いうようなことには、まったくならなかった。貴重な証人によって日の下に晒された真実がおもしろく、我々は手を叩き、身をよじらせて笑ったのである。新郎が、我々相手につまらない見栄を張っていたという事実もまた、愉快で仕方なかった。
これはもっと他にも、何か出てくるかもしれない。
そんな我々の興味を一身に集める形で、それまで聞き役に徹してた「新郎 中学同級生」の彼が一躍テーブルの主役の座に躍り出た。何といっても、この場で唯一の「真実を知る者」なのだ。また彼が、よく喋った。「お皿を相手に、呟き芸の練習でもしに来たのかな?」と思わされた初めの頃とは、別人のようだった。
そんなわけで、新郎新婦の新たな門出を祝うはずの結婚式は、思わぬ形で新郎の過去が暴かれる場となった。改めて考えて見ると、ひどい話である。ただ、原因を作ったのはつまらない嘘を吐いた新郎自身だし、さすがに新郎新婦の前でその話を持ち出すような狼藉を働く輩はいなかったから、大目に見てもらいたいところだ。
たくさんの暴露話をしてくれた「新郎 中学同級生」とは、披露宴が終わる頃には、随分打ち解けることができた。
少なくともこちらはそう思っていたのだが、彼の方ではそうでもなかったらしい。二次会にも誘ったのだが、即答で断られてしまった。
同級生たちは残念がっていたが、僕は一人心の中でうなづいてもいた。
このやたらに固い心のガードも、人見知りの特徴の一つだからである。