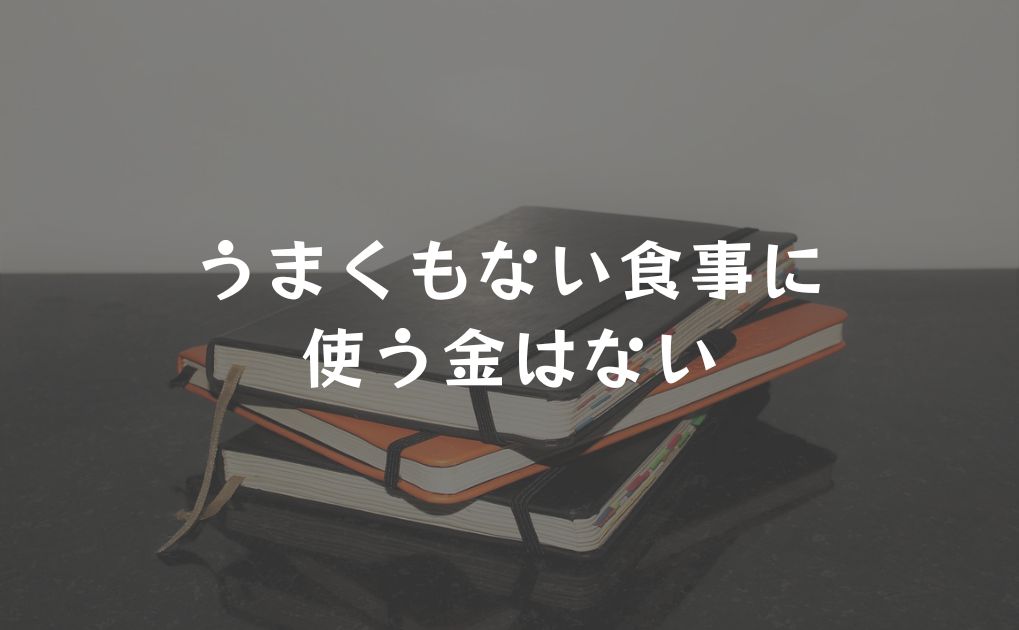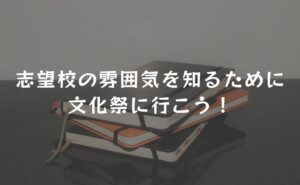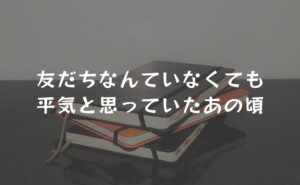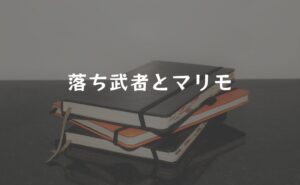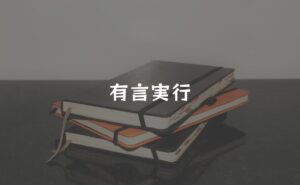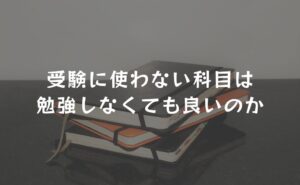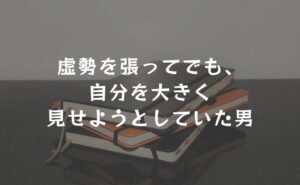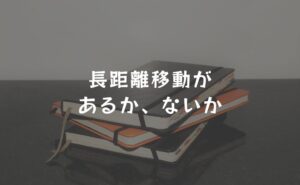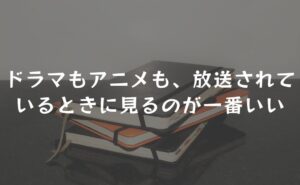そこそこの年月社会人をやっていると、「世の中には、こちらの常識の範囲からはみ出したヘンな人が割とたくさんいるな」ということがわかってくる。
深酒をして終電を逃し、会社で一晩明かした上に始業時刻になっても目を覚まさず、昼まで床で眠り続けていた人。一度も目を通していない資料を取引先に持って行き、その場でその資料の説明を始めた先輩。会社から貸与されたスマホにゲームをインストールして遊んでいた後輩もいれば、「外付けハードディスク」と言い張って、会社の金で携帯ゲーム機を購入していた同期なんかもいた。
入社三年目に初めて人事異動をした先で知り合った先輩も、そんな奇人の一人だった。正確な年齢は聞いたことがなかったが、多分四十代前半くらいだったんじゃないかと思う。独身で、役職には付いておらず、四角いメガネをかけていて、頭髪は大分薄くなっていた。みんながスーツで出社するのが当たり前の職場に、一人だけカジュアルなシャツとチノパンという姿でやってきていた。
「別にスーツで来る必要ないでしょ。営業部と違って、客のところに行く仕事じゃないんだから」
先輩は、スーツを着てこない理由をそのように説明していた。そしてこの言葉にこそ、先輩の際立ってイカれた点がよく現れているのであった。
先輩は、徹底した合理性の信奉者だったのである。
「まあでも、そういう人いるよね?」と思われた方もいるかもしれない。確かに、合理的な考え方をする人というのは世の中にごまんといる。しかし実際にその思考が行動に結びついているかと言うと、意外とそうでもなかったりする。自分では「合理的じゃないからやりたくない!」と思っていることでも、会社の方針とか、上司の命令とか、周囲からの同調圧力とかでやらざるを得ないことも少なくないだろう。
でも先輩はそうではない。会社の方針だろうが上司の命令だろうが、お構いなしだ。自分が「無駄」「意味がない」と判断したことには、指一本動かしてはくれないのである。同調圧力などはもはや、春先に頬を撫でるそよ風と同じだ。「屈しない」という話ではなく、感じてすらいないのではないか、と思わされることが何度もあった。
一度、とんでもなくびっくりしたことがある。
部門全体でやる忘年会の、日程調査の連絡が回って来たときのことだ。
その年はどういうわけだか幹事がものすごくやる気を出してきて、9月から予定の調整が始まっていた。忘年会が開催されるのは12月だから、三ヶ月近く先の予定を調べていたことになる。
「早めに場所を確保しておくために人数を知っておきたい」と幹事は説明していたが、9月の時点で12月の予定がすべて埋まっている人など普通はいないから、実際には「全員参加できる日に設定するから、予定は空けておけよ」ということを暗に伝えていたのだった。誰かえらい人に、「今年の忘年会は全員参加でやりたいね」とか言われたのだろう。
日程調査の内容は、「12月の金曜日で空いている日を教えてほしい」というものだった。共有サーバに、Excelで作成した「縦が社員名、横が12月の金曜日」という簡単な表が置かれていて、各自がそれに〇×で予定を記載していくのである。大抵の人は、すべての空欄が〇になった。まだ9月なのだから当たり前である。でも先輩に、そんな常識は通用しなかった。幹事の意図も、その向こうに透けるえらい人の希望もどこ吹く風だ。先輩はすべての空欄に、ためらいなく×を記入していたのである。
先輩がものすごいのは、日程調査の案内が回ってきた瞬間にそれをやってしまっているところだった。そういうエクストリームなふるまいに走る場合でも、もう少し周りの様子をうかがって実行に移すのが普通なんじゃないかと思う。今回のケースで言うなら、予定を報告し終えた人の多い締め切り間際に「全×」を記入するとかだ。そうしておけば、自分の過激な行為も多くの人の目に触れずに済む。自分の分を記入し終えた後に再びExcelを開く人は、幹事くらいだからだ。
しかし先輩は、そんな小さいことを気にする人ではなかった。誰よりも早くExcelを開き、幹事以外まだ誰も予定を入れていない表に、すごい速さで×をコピペしまくっていたのである。
「社内の飲み会なんて時間の無駄だよ」と先輩はよく言っていた。
「アレに言ったって人脈広がらないじゃん。飲み会に行くなら社外の人と行くんだよ」
その言葉通り、先輩は社内で行われるあらゆる飲み会に欠席していた。忘年会も新年会も、歓迎会や送別会ですら例外ではなかった。「合理性」の塊である先輩は、飲み会にすら意味を求めていたのである。楽しく酒を飲んでバカ騒ぎをするなんて、先輩からすると時間の無駄でしかないのだ。
ランチのメニュー選択にも、先輩の「合理性」は、遺憾なく発揮されていた。先輩が選ぶものは、「社員食堂の日替わり定食の安い方」と決まっていたのである。
「社食のメニューなんてどれも大してうまくない。うまくないものに金をかけるのは無駄だ。と言っても、毎日同じものを食べていたら飽きるし、栄養も偏る。だから日替わり定食の安い方を選ぶのだ」
というのが、先輩が教えてくれた理屈であった。まだ若かった僕は、大変感心しながらその話を聞いていた。昼飯選びを、そんな風に考える人に出会ったことがなかったからである。
仕事の方でびっくりしたのは、先輩が呼ばれた会議や打ち合わせにあまり参加しないということだった。と言っても、先輩が別にサボっていたわけではない。会議や打ち合わせの予定がスケジューラに入れられているのを確認したとき、先輩はいつも、間髪入れず開催者に電話を掛けた。そこで議題と目的を聞き出し、自分の出席が必要かどうかを判断していたのである。
その結果、出席不要となることも多かった。中にはその電話で用事が済んでしまい、打合せそのものがなくなることもあった。「だってあいつら、何となく呼んでるだけだもん」と先輩は言っていた。「それに付き合って何となく参加してたら時間の無駄じゃん。だから事前に確認しておくんだよ」なるほどなあ、とまだ若かった僕はここでも感心した。ただちょっと真似はできないかなあ、とも思った。
そんな先輩だったから、誰かに仕事を依頼されても簡単には首を縦には振らなかった。先輩に何かをやってもらうには、「それが無駄でなく、意味がないものでもないこと」を納得してもらう必要があるのだ。相手が直属上長であっても、それは同じだった。そしてまた厄介なことに、先輩はえらく弁が立つ人だった。課長が先輩に言い負かされている姿を、何度か見たことがある。
まるで昨今流行りの「論破系新入社員」だ。ただ、先輩が彼らと大きく違っていたのは、自分が納得した仕事についてはきちんとこなす、ということだった。それもただやっつけるのでなく、仕事は早いし、アウトプットには決まって質の高いものが出てくるのである。
先輩は、決して口だけの人ではなかったのだ。だからこそ、ちょっと極端とも思えるあの「合理性」も許されているのだろう。『こち亀』の両津勘吉なんかと同じだ。
と、若く未熟な当時の僕は無邪気に思っていた。でも実際は、そうでもなかったようだ。課長からするとやはり、先輩は扱いにくい部下でしかなかったらしい。飲み会の席で愚痴をこぼしているのを聞いたことがある。
一緒に仕事をしている人たちからの評価も、おおむね似たようなものだった。「仕事はできるけど、やりにくい人」というのが、周りから見た先輩だったのである。「先輩がいた方がスムーズに進むけど、いなくても何とかなる仕事なら面倒だから呼ばない」というケースも、実は結構あったようだ。それはすなわち、合理性を追求した先輩のふるまいが、周りに「合理的でない方」を選択させる要因となっていた、ということにもなる。皮肉な話だ。
そういう職場の空気が先輩にも伝わっていたのか、僕が配属になって一年が経った頃、先輩は社内公募を利用して別の部署に異動して行ってしまった。元々社内公募で来た人らしいので、「社内公募でやってきて、社内公募で出て行った」ということになる。送別会は、もちろんやらなかった。一応、僕が幹事を任されたので先輩に打診はしてみたのだが、「やってほしいと思う?」と笑いながら言われてしまった。
若い頃の僕は、先輩の徹底した合理性にしきりと感心していた。でも今は、自分の嫌いなことを避けるための方便として、「合理性」を都合よく使っていた面もあったんじゃないかという気もしている。
人脈を作ることだけが飲み会の目的ではないし、社食がうまくないと思うなら、うまいものを会社の外に食べに行けばいいだけの話だからだ。
おそらく先輩は会社の飲み会が嫌いで、ランチにお金を使いたくない人だったのだろう。そうした自分の卑小さを、「合理性」という便利な言葉で飾っていたに過ぎないのだと思う。
仕事の方も、ちょっと疑わしいと思っている。先輩は、仕事はできたがやる気のある人ではなかったからである。
意味のない仕事や無駄な作業というのも、確かにあった。でも単に、面倒くさいからという理由で断っていたものもあったんじゃないか、と思っている。