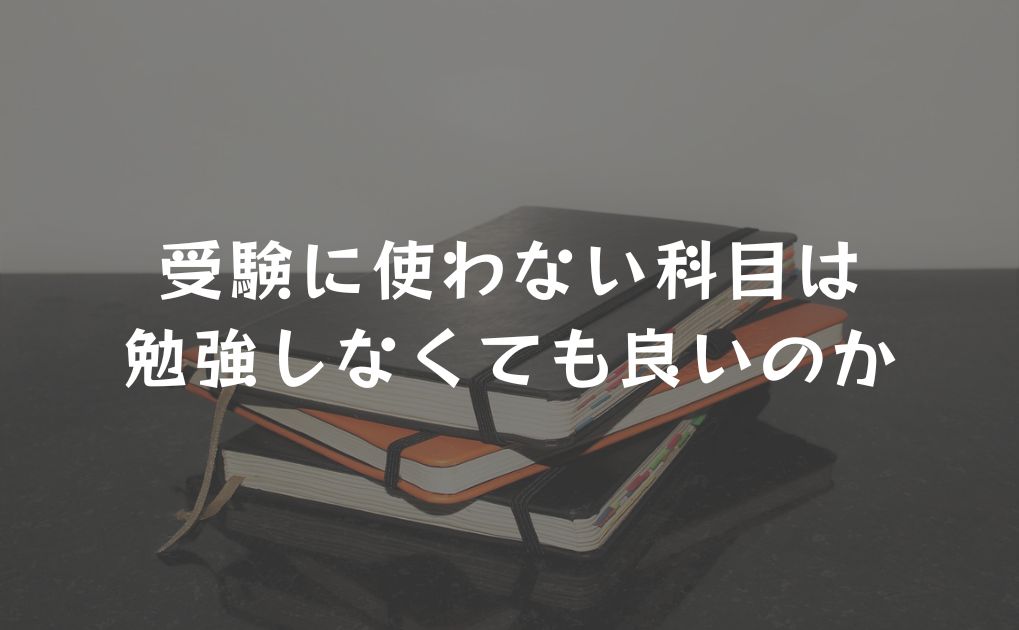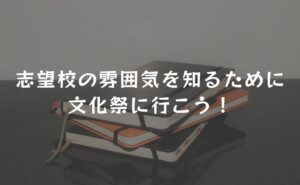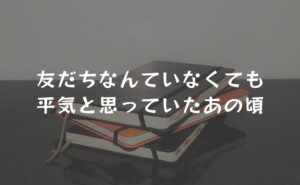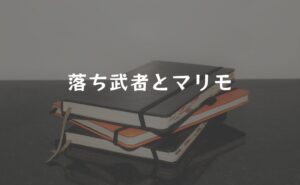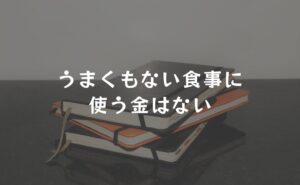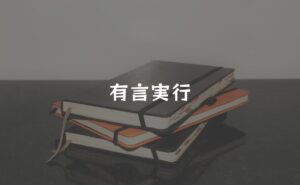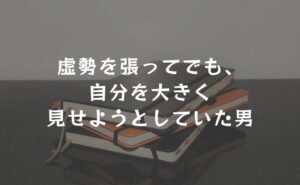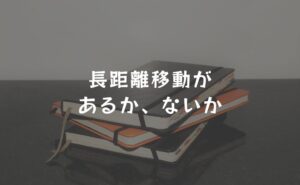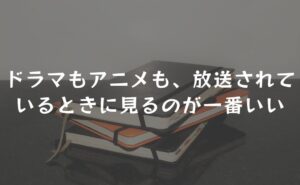今はどうだか知らないが、僕が高校生の頃の必修科目に「世界史」があった。
日本史は選択科目だったのに、世界史だけが必修になっていたのである。
「日本史が必修の方がいいんじゃないかな? 日本の学校なんだし」と思わないでもなかったが、おそらくは「日本史は小学校と中学校でも勉強してるから、選択でよい」ということだったのだろう。「世界史は高校に入るまで機会が少ないから、必修にしている」と言われたら、一応筋が通っているようには聞こえる。
だからと言って、大学受験を控えた高校生にとっては迷惑極まりない話であることに変わりはないのだが。
入試に世界史を使わない高校生、割とたくさんいる。理系志望の場合はほとんど、と言ってもいいくらいかもしれない。そもそも彼らは、「地理歴史・公民」にほぼ用がない。出番があるのは、センター試験(現在の大学入学共通テスト)くらいだろう。
その場合でも、理系学部では「地理歴史・公民の中から一科目を選択」というケースがほとんどになっている。この中から、あえて世界史を選択しようというのは、よほどの歴史好きか変わり者と言っていい。というのも、「地理」や「公民」と比べて「歴史」は覚えることが多く、その上世界史は同じ「歴史」の日本史より勉強量が必要と言われていたからである。
理系のメインディッシュは、言うまでもなく数学や理科だ。前菜に過ぎない地理歴史・公民は、なるべく労力をかけずに高得点が期待できる科目を選びたい、というのが、理系学部への進学を希望する学生の、普通の考え方なんじゃないかと思う。
でも現実は、それを許してはくれないのである。
僕の通っていた高校では、2年生ときに理系、文系のクラス分けが行われた。そして世界史の授業が始まるのも、2年生からなのだった。僕は理系を選択していたがその時間割にも、当然世界史は存在していた。と言っても、その世界史は文系クラスのものとは違っていた。
理系と文系で、授業を担当する教師が違っていたのである。
文系の世界史は、クラス担任もやっているベテラン教師が担当した。一方理系には、新任の非常勤講師が充てられていた。
実に露骨な格差配置だった。でも僕は、そのことを特に腹立たしくは思わなかったし、それは理系を選択したすべての生徒も同じだった。むしろ「学校側も良くわかっているな」と感心してしまった。受験に不要な科目の授業がどのようなものになるかということを、十分に理解した人員配置という感じがしたからである。
僕たちの世界史を担当することになった新任の非常勤講師は、田辺先生(仮)と言った。田辺先生は小柄で瘦せていて、見るからに気が弱そうな人だった。見た目に違わず声も何だかか細くて、「人前で喋るのがあんまり得意じゃないのかな」という、教師らしからぬ印象を与える人でもあった。
初めの頃は、授業もとてもぎこちなくて、「この人、これでやっていけるのかな」という余計な心配を抱かされたりもした。
ただ、では肝心の授業も退屈で聞く価値に乏しいものだったかというと、意外とそうでもなかった。
話し方はともかく、その内容は割とおもしろかったのである。
先生の授業は、歴史に対する情熱みたいなものに溢れていた。「この人はきっと歴史が好きなんだろうなあ」という感じが言葉の端々に滲み出ていたし、「その楽しさを伝えたい」という意欲も強く感じられた。話し方が上手でないのは事実だったが、その分、板書は教科書の内容がわかりやすくまとめられていたし、補助教材のプリントなんかもたくさん作ってくれていた。歴史好きというだけでなく、教育にも熱心な先生という感じがした。
回を重ねるうちに、僕は先生の授業が楽しみになってきていた。大学受験の役には間違いなく立たなかったが、それもそんなに気にならなくなっていた。
でも残念ながら僕みたいなタイプは、クラスでは圧倒的な少数派だった。クラスメイトのほとんどは、田辺先生の授業を聞いていなかったのである。彼らは世界史の時間を、「理系のメインディッシュ」の科目や、文理問わず必要になる英語の勉強に充てていた。世界史の授業は、最初から聞く気すらないのだった。
授業を聞いていないのだから、その内容がおもしろいかどうかもわかるはずがない。田辺先生の熱意も、彼らにはまったく伝わってはいなかっただろう。
これを田辺先生の力量不足と言ってしまうのも、酷な話だ。こうした状況が発生してしまうのは、大学入試に使われない科目の宿命みたいなものだからである。どんなベテラン教師が担当しても、似たような状態になったんじゃないかと思う。ただちょっと不幸だったのは、若く、教師になりたての田辺先生が、そうした「理系の世界史」をどうやらよく理解せずに担当していたことだった。
「ほとんどの生徒が自分の授業を聞いていない」という現実は、田辺先生の心をじわじわと蝕んでいたらしい。
異変の兆候は、一学期の終わりくらいから現れていた。授業をしている先生に、何だか元気がないように感じられたのである。二学期に入ると、その変化は顕著に現れ始めた。あれほどたくさん作ってくれていた副教材のプリントが、まったく配られなくなってしまったのだ。板書の内容も、一学期と比べると大雑把なものへと変わった。
田辺先生は明らかに、授業の質を落としていた。
それも仕方ないのかな、と僕は思った。
先生はきっと、教師という仕事に大きな希望を抱いていたのだろう。初めの頃の熱意を見れば、それはよくわかる。教員採用試験に合格できなくても教師の道を続けようとしているくらいだから、それなりに高い志も持っていたんだと思う。「一人でも多くの生徒に、世界史を好きになってもらいたい」とかも、考えていたのかもしれない。
でも現実は、この有様だ。1クラス45人のうち40人は、50分間の授業中一度も顔を上げずに違う科目の勉強に勤しんでいる。これでやる気を維持し続けろという方が、無理な話だ。
これは一体、誰が悪かったのだろう。当時のことを思い出すたびに、僕は考える。
授業をまったく聞かない、理系クラスの生徒たちだろうか。新任の教師を理系クラスに割り当てた、高校だろうか。それとも、「理系クラスの世界史」に対する認識の甘い先生に問題があったのだろうか。
大学受験を控えた高校生たちが、時間を可能な限り有効に使いたいと考えるのは当然だろう。理系クラスにベテランを割り当てた場合、文系の方に新任を割り当てることになる。その体制が歪なことは、誰の目にも明らかだ。
やる気のない生徒相手の授業であることを覚悟していたら、先生の失望はなかったのかもしれない。でもその場合、一学期の授業で見せてくれたような先生の情熱が、僕たちに伝わることもなかっただろう。僕と同じように先生の世界史をきちんと聞いていた数少ないクラスメイトたちの間では、田辺先生の授業のおもしろさは共通認識となっていた。
やがて先生は、板書そのものもやめてしまった。世界史の授業は、先生がただ教科書を読み上げるだけの無味乾燥な時間と化してしまったのである。
授業に慣れて少し大きくなっていた先生の声も、元の小さく聞こえづらいものに戻ってしまった。田辺先生の授業を楽しみにしていた僕はちょっと残念に思いながら、家から持ってきた数学の問題集を机に広げたのだった。