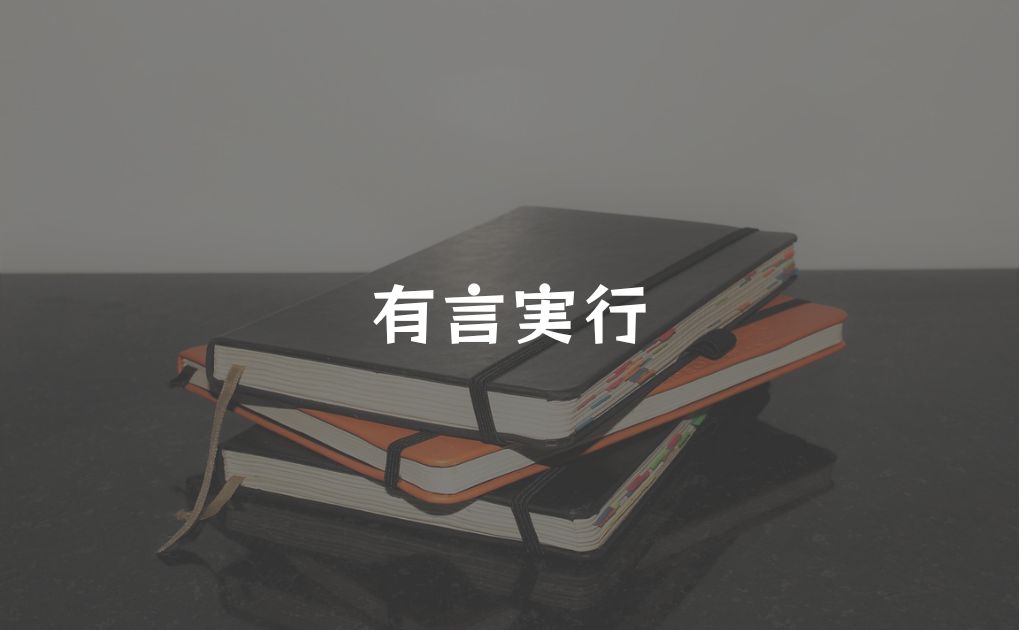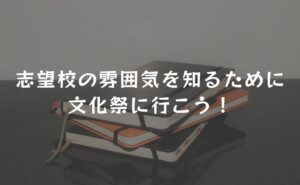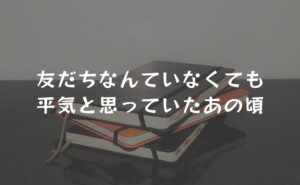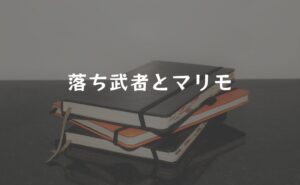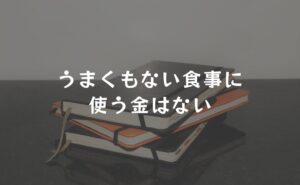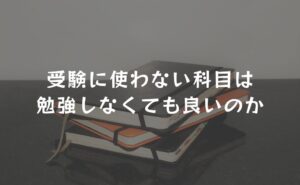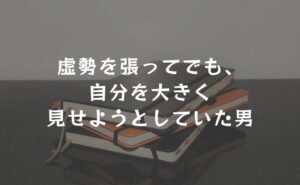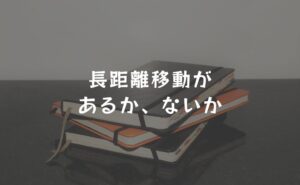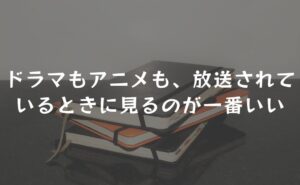小学校卒業を間近に控えた六年生の三学期、何かの授業で「中学生になったらやりたいことを発表しよう」ということになった。「そんなもの共有しあったところで何になるんだ」と思ったが、授業でやるというのだから仕方がない。
幸い、ネタには困らなかった。中学校に入ったらやりたいことは、既に決まっていたからである。
「中学に入ったら、バスケットボール部に入ろう」と僕は思っていた。当時好きだったマンガの影響で、バスケをやってみたいと思っていたのだ。
発表会当日、僕はその希望を包み隠さず公表した。
教室は、地震が起こっているんじゃないかと思うくらいの爆笑で揺れた。
バスケと言えば、野球やサッカーと並ぶ、花形スポーツだ。そんな人気競技に、小太りで背も低く、運動能力もクラスで一、二を争うほどに低かった当時の僕が挑戦しようというのが滑稽だったのだろう。
でも僕は、特にそのことを恥ずかしいとは思わなかった。そういう反応があるだろうことは、事前に予想できていたからである。誰に何を言われようと、自分がやりたいのならやればいい。そう考えていたから、みんなに笑われたことで入部をためらう気持ちも起こらなかった。
そうして小学校をつつがなく卒業し、当たり前のように地元の中学校に進学した僕は、迷わずバスケットボール部に入部届を提出した。
小学校での発表会の後、「実はオレもバスケ部に入ろうと思ってるんだ」とこっそり伝えてきたクラスメイトがいた。発表会ではバスケ部の話はしていなかったのだが、そのときはまだ迷っていたらしい。練習についていけないかもしれない、という不安があったのだそうだ。僕たちの進学する中学校のバスケ部は、練習が厳しいことで知られていたのである。
「お前の発表を聞いて、迷いが吹き飛んだよ」とにこやかに語ってくれた彼を、僕は内心冷ややかな目で眺めていた。「お前みたいなチビデブがやるなら、オレにもできるだろう」という本音が、透けて見えていたからだ。
でも結局、彼とは同じ部活にならなかった。仮入部期間を経て、彼は練習がマイルドなことで有名な別の運動部に入部していたのである。
僕は別に「裏切られた」とは思わなかった。初めから、彼を当てになどしてはいなかったからだ。ただ、入部してみてしみじみ思ったのは、彼の判断もあながち間違いではなかったのかも、ということだった。
バスケ部の練習は、噂にたがわぬ厳しさだったのである。
入部してしばらくの間は、とにかく走らされた。学校の周りを、ひたすらぐるぐる回るのである。走って走って、また走った。この時期の僕たちは、陸上部よりも走っていたんじゃないかと思う。バスケ部なのに、体育館にいない時間の方が長いくらいだった。おかげでぽっちゃり体系からはあっという間に脱出できた。
体育館での練習も、ツラいメニューの方が多かった。
最も楽しいゲーム形式の練習は、食後のデザートみたいなものだった。練習の最後にちょろっと出てくるくらいで、時間も短い。それ自体がない日もしばしばあった。
では一体何をメインでやっていたかと言うと、これまた大半が基礎練習だった。その場にとどまってひたすらボールを床に打ち付けるドリブル練習に、二人一組で延々と繰り返すパス練習。プレー中の足さばきを鍛えるフットワークに、持久力と瞬発力を鍛えるシャトルランなど、とにかく地味でキツい嫌がらせみたいなラインナップがこれでもかとばかりに取り揃えられていたのである。
「うまくなりたい」とか「試合に出たい」といった健全な気持ちは、結構早い段階で吹き飛んでいた。
とにかく練習がキツ過ぎて、頭の中は「部活嫌だな」とか、「練習行きたくないな」とか、「天変地異が起こって体育館が吹き飛んで、校庭も地割れだらけになった部活中止にならないかな」とかの、ネガティブな考えでいっぱいになっていたのである。
「今日は部活サボりたいな」と思った日も、一度や二度ではない。でも一度も、それを実行に移したことはなかった。サボった後が、恐ろしかったからである。
僕が通っていた中学校の男子バスケットボール部は、小柄で若い、女の先生が顧問をやっていた。年齢は、おそらく30歳前後だったのではないかと思う。
男子バスケットボール部の女性顧問というと、何となくバスケ未経験のお飾りを想像するかもしれない。でも、先生は違っていた。学生時代はバスケの選手だったらしく、技術面の指導もできる人だったのである。
僕の中学校には、女子バスケットボール部もあった。でも先生は、あえてそちらは選ばずに男子の方を選んだという話だった。それだけに、かなり強烈な人でもあった。
先生は、いつも不機嫌そうに顔をしかめていた。眉間に深い縦しわが寄っているのがデフォルトで、身体は大きくなかったものの、面と向かうとものすごい迫力があった。こちらに視線を向けられると、思わず後じさりしたくなってしまうほどだった。
練習中、気の弱い先輩が怒鳴られて泣きべそかいている姿を僕は何度も目撃している。
今なら大問題になりそうな指導法が炸裂したことも、何度かあった。最もよく覚えているのは、僕たちが3年生だったときの、ある公式戦の真最中の出来事だ。
バスケットボールは試合の途中に、「タイムアウト」という作戦タイムを取ることができる。タイムアウト中はプレーが中断され、コートに出ていた選手たちも一度ベンチに戻る。このときに先生はあろうことか指示されたのと違うプレーを繰り返していた選手の頬に、ビンタを食らわせたのである。
先生が周到だったのは、ビンタの直前に控えを含めた選手全員で先生とその選手の周りを囲ませていたことだった。目隠しのバリケードを作らせていたのである。今より緩い時代だったとはいえ、公式戦の最中に顧問が選手に暴力を振るったことが公になれば問題にはなりかねない。それを防ぐためだったのだろう。
もっとも、平手打ちが炸裂した瞬間に結構派手な音が響いていたので、気付いた人もいるんじゃないかと思う。
そんな鬼の顧問からの叱責が、部活をサボった翌日には待っているのである。ほんの数か月前まで小学生だった当時の僕に、部活をサボろうなんていう勇気が湧いてくるはずもなかった。ツラくても練習に参加する方が、なんぼかマシである。
「そんなにしんどいなら、やめればよかったのでは」と思われるかもしれない。
確かにその通りだ。でもどういうわけか当時の僕は、そういう発想にはまったく至らなかった。どんなにツラくてもバスケ部は最後まで続けるのだ、という謎の執念に取りつかれていたのである。
その気持ちは三年間衰えることなく、結局僕は三年の夏、最後の大会に負けるまで部活をやり抜いた。しかし哀しいかな、そうした「不器用な気真面目さ」みたいなものは競技の実力とは必ずしも結びつくものでもなく、厳しい練習に耐え抜いた割に、僕のバスケットボールの実力は大して向上してはいないのだった。現実はそんなに甘くはない。
一年生のときはもちろん、一度もベンチに入れなかった。そしてそれは、二年生に進級しても変わらなかった。二年生の夏、三年生が引退した後に初めてユニフォームをもらったが、背番号は哀しみの二桁だった。バスケは一チーム五人でやるスポーツなので、自分たちの代のときの主力はほぼ間違いなく背番号が一桁になる。それが二桁ということは、大して戦力になっていないことの証だ。
同期が五十人くらいいたなら、それでも十分上等ということになっただろう。二桁どころか、ユニフォーム自体をもらえない部員だっているからだ。でも当時の男子バスケ部に、僕の同期は九人しかいなかった。最上級生になれば、自動的にユニフォームはもらえてしまうのだった。
そんなわけで、僕のバスケ部員としての三年間はお世辞にも成功と呼べるものではなかった。小六のときに僕を笑ったクラスメイトたちが見たら、「やっぱりね」と言いたくなる結果だったんじゃないかと思う。
高校では、僕はバスケ部に入らなかった。他にやりたいことがあったからだ。そのため、一年生の体育でバスケをやることになったときには、随分久しぶりな気がした。
授業でやるバスケだから、もちろんそんなに本気ではない。未経験者も多いし、お遊び程度のものだ。そんなことはわかっていたのに、つい僕は張り切ってやってしまった。同じチームにバスケ部の同級生がいて、少しは形になったプレーができたことも、意図せぬ僕のハッスルに大きく関与していた。
授業の後、その元バスケ部の同級生に声を掛けられた。
「滅茶苦茶楽しそうにやってたね。バスケやるの、好きでしょ?」
その言葉には、僕ははっとさせられた。自分はバスケットボールをするのが好きなのだと、そのとき初めて気が付いたからである。バスケ部に在籍していた中学生のときは、毎日の練習を乗り切るのに必死で、バスケが好きかどうかなんて考えたこともなかった。
でも改めて誰かに言われてみると、確かにその通りだった。僕はバスケをするのが好きなのだ。
スポーツが苦手だった僕がそう思えるようになれたのは、中学三年間の部活があったからだ。そう考えると、いまいちな結果しか残せなかった三年間だけど、やめずにバスケ部を続けておいて良かったなと思っている。