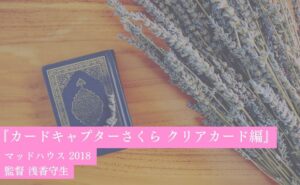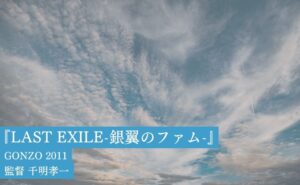| サムライフラメンコ マングローブ 2013 |
| 監督:大森貴弘 |
| 原作:manglobe シリーズ構成:倉田英之 キャラクター原案:倉花千夏 音楽:玉井健二 & agehaspringsKENJI TAMAI & agehasprings OPテーマ:SPYAIR「JUST ONE LIFE」/FLOW「愛愛愛に撃たれてバイバイバイ」 EDテーマ:ミネラル★ミラクル★ミューズ「デートTIME」/「フライト23時」 キャスト:増田俊樹・杉田智和・戸松遥・M・A・O・山崎エリイ |
『サムライフラメンコ』は2013年10月から2014年3月にかけて、フジテレビ・ノイタミナ枠で放送されたマングローブ制作のオリジナルアニメです。
マングローブは2004年に『サムライチャンプルー』という作品を制作していますが、本作と「サムライつながり」とかではありません。全然別の作品です。
本作、ちょっとクセがあります。
大森貴弘監督は『夏目友人帳』や『地獄少女』などの人気作品も手掛けていますが、この『サムライフラメンコ』は大分異色の作品と言っていいんじゃないかと思います。タイトルからして、「サムライ」と「フラメンコ」を並べるという意味のわからなさですしね。
見たことある人の中には、「迷走」を感じた人も少なくないんじゃないかと思います。私はそんなに否定的じゃないんですが、それでも途中からの急展開には戸惑いました。
そのせいもあってなのか、一時期は配信もFODでしかなかったんですが、今(2023年8月時点)はdアニメストアやU-NEXTなんかでも見られるようになってるみたいです。
『サムライフラメンコ』概要
『サムライフラメンコ』の主人公は、物語開始当初19歳、男性ファッション誌でモデルをしているイケメンの羽佐間正義です。
芸能人なので、住んでいるのも広いマンションです。もっとも、それ自体は事務所が借りているものであって、正義の資産ではないのですが、そんな事務所の人たちにも知られていない秘密を彼は持っています。
それは、幼い頃から続いている筋金入りの特撮ヒーローマニアであること。
イケメンモデルからは想像しにくい趣味ですが、もちろんただ好きというだけなら何の問題もありません。でも彼の場合はそれだけでは終わらなくて、何と好きをこじらせた結果、個人で勝手に「正義の味方活動」を始めてしまうのです。
まあ、意味不明ですよね。個人で正義の味方活動って。でも正義は大まじめでそれに取り組んでいます。
作品のタイトルにもなっている「サムライフラメンコ」とは、正義が「正義の味方活動」をするときに扮するヒーローのことです。これも彼が考えて、勝手に名乗り始めました。
ただ、これもまた非常に残念な話なのですが、正義はただの特撮ヒーローマニアなので、生まれついての特殊能力があるわけでもなく、どこかで改造手術を受けたわけでもなく、格闘技の経験があるわけですらありません。
それどころか正義の非力ぶりは見ていて哀しくなるほどで、相手が一般人でも簡単にやられてしまうのですね。
正直、「何でそれでヒーロー活動やろうと思った?」と聞きたくなってしまうほどです。
『サムライフラメンコ』には、もう一人の主人公と言ってもいい警察官の後藤英徳というキャラクターがいて、この後藤と正義が出会うところから物語は始まります。
このときも正義は「正義の味方活動」に失敗しており、何と身ぐるみはがされた全裸の状態で、そんな正義を見て後藤は「変態だ!」と力強く叫ぶのでした。
『サムライフラメンコ』レビュー

※タップすると楽天のサイトに移動します。
第7話でガラリと変わる空気
冒頭でも紹介した通り、『サムライフラメンコ』はちょっとクセのある作品です。
その要因の一つとなっていたのが、第7話から急に作品の空気が変わることだったんじゃないかと思います。
第6話までは、モデルで特撮ヒーローマニアの主人公羽佐間正義が「個人で正義の味方活動をやっていること」を中心に物語が回っていました。
- 正義が成長して「正義の味方」らしい活動ができるようになる
- 同じような活動をしているライバルが登場する
といった変化はあったのですが、正義たちの活動はあくまで個人的なものであり、大人が楽しむ「正義のヒーローごっこ」という部分は変わりありませんでした。「正義の味方活動」と言っても、守っているのはあくまで「手の届く範囲」であり、倒すべき悪は街のルール違反や迷惑行為、軽犯罪くらいだったんですよね。
警察官である後藤は正義たちの後始末や尻拭いに奔走させられるのですが、6話くらいまでそういう展開が続くと、見ている我々も、
「ああ、この作品はこうやって、ヒーローマニアの青年たちが現実の世界で行うこじんまりとしたヒーロー活動(ヒーローごっこ)と、それに振り回される後藤の様子を楽しむんだな」
と考え始めるわけです。
悪の組織も怪人も存在しない現実の世界で、ヒーローごっこをする若者たちの姿をコミカルに描いた作品なのだな、と。
ところが第7話で、そうした認識が一気に覆されます。
これは『サムライフラメンコ』を見たことがある多くの人がうなづくところだと思うのですが、この作品でそれはないだろう、というような事態が発生してしまうのですね。
「うん? あれ? これ、そういう話?」という戸惑いと、そして作品の先行きに対するかすかな不安がここで生じます。ですが、本作にはそれをそこだけでとどめてくれるような優しさはありません。
ここで生まれたわずかなひずみは、その後修正する気配を見せないまま、どんどん膨らんでいきます。見ているだけの我々に、それを止める術はありません。「自分は一体、何を見せられているんだ?」そんな思いを抱えたまま、あらぬ方向へ運ばれていくのただ感じているしかない。
未視聴の方には何を言っているのかさっぱりわからないと思いますが、でも実際のところそうなのです。第7話に与えられたサブタイトルは「チェンジ・ザ・ワールド」なのですが、その言葉そのままに、ここで一気に作品の進む方向が変わってしまいます。
迷走し過ぎて見るに堪えない?
第7話以降の展開をもって、本作を「迷走しまくった作品」と考える人もいると思います。
確かに、そう見えてしまうのも仕方がないとは思います。実際のところ、私も見ていて戸惑いは覚えました。
でも、じゃあ迷走し過ぎで見るに堪えない作品だったかというと、そんなことはなかったと思うんですよね。結構最後まで楽しめる作品でした。
その大きな理由になっていたのが、どんなときにもコミカルさを失わなかったというところだったと思います。この点については、迷走はなかったですね。終始一貫していて、見事に一本芯が通っていました。
『サムライフラメンコ』は、基本的にコミカルな作品です。そもそも主人公が19歳にもなって、特撮ヒーローに憧れるあまり個人で「正義の味方活動」を始めてしまうような人物ですからね。
コミカルな場面は、作品のいたるところに用意されていました。また、「ここからシリアスになっていくのかな?」と思いたくなるような終わり方をした回でも、次のエピソードでは元の愉快さに戻っているという抜群の復元力も見せてくれました。
これについては、第7話で「チェンジ・ザ・ワールド」したあとも同じです。中盤以降は特に、特撮ヒーロー番組のパロディが多くなっていました。
少なくとも、見ていて「退屈」と感じさせる作品ではなかったと思います。
本当に必要な「ヒーロー」とは
『サムライフラメンコ』でもう一つ注目すべき点は、正義が現実の世界で「正義の味方活動(=ヒーロー活動)」をやろうとしたことから直面する問題です。
正義が憧れている特撮ヒーローは、
「番組が与えてくれるシンプルな勧善懲悪の世界で、善の立場で行動すればOK」
という存在でした。テレビ番組ですからね、当然です。
でも、現実はそうシンプルではありません。特撮ヒーロー番組ではまったく存在感のない、法律や警察が存在するからです。
実際のところ、特撮ヒーローが存在しなくても現実の秩序はある程度保たれてはいるんですよね。むしろ、正義の「正義の味方活動」が、余計なものを生み出してしまっている部分もあります。
そうなると浮かんでくるのは、
「特撮番組でない、現実の社会で本当に必要なヒーローとはどんな存在なのか」
という問い。
コミカルだし、迷走も疑われてしまっていますが、その疑問に対する答えも作品はしっかりと提示しています。
ヒロイン?の真野まり

※タップすると楽天のサイトに移動します。
『サムライフラメンコ』の主人公である正義と、もう一人の主人公である後藤は、正義が身ぐるみはがされて全裸のときに、後藤に発見されることで出会います。
二人はその後仲良くなり、特に正義は後藤をとても慕っています。その態度は、まるで後藤を恋人と考えてでもいるかのようです。
実際、後藤は正義のよき理解者ですし、年上で頼りになる存在ではあるんですよね。
でもじゃあ二人のそうした関係が(といっても、後藤は少しもそういう感じではないのですが)、いわゆる「作品の華」になるのかというと、そんなことはありません。
何だか妙な気分になって、どこに持って行ったらいいかわからない感情の行き場となってくれるのが、3人組のアイドルグループ「ミネラル★ミラクル★ミューズ」です。
正義は芸能事務所に所属しているので、彼女たちとも接点があるのですね。特にセンターの真野まりは、作品の主要登場人物の一人でもあります。
ただ、では彼女が本作のヒロインかというと、これがまたシンプルにそうとは言い難いところがあります。というのも彼女、ただのアイドルというだけではなく、正義がやっている「正義の味方活動」に大きく関係してくる人物でもあるのですね。
系統的には、正義と同種の人間と言っていいと思います。違いは、まりの方がより過激なところですね。
後藤は本作の中では常識人として描かれており(実際には、これもちょっと違うのですが)、最初は「そうではない」正義に振り回されます。
その正義もまた、自分以上に「そうではない」まりに後藤と一緒に振り回されることになります。
まりについては「真のヒーローとは何か」にかかわる重い展開も用意されているのですが、少なくとも序盤は彼女と後藤たちとのドタバタを楽しむ作品になっています。
『サムライフラメンコ』まとめ
何度も書きますが、『サムライフラメンコ』はとにかく第7話以降が大変です。
振り回されまくりますし、迷走と思ってしまってもおかしくないくらいの状況が現出します。
もっと色々書きたいところではあるのですが、あまり説明してしまうと今度は見る楽しみが失われてしまうと思うので、このくらいにしておきます。
気になった方はぜひ、自分の目で確かめていただければと。
その上で、迷走していたかどうか判断していただければと思います。
この記事を書いている2023年8月時点では、U-NEXTやdアニメストアの見放題が復活していたので、見るのにそれほどハードル高くないんじゃないかと思ってます。
| タイトル | 『サムライフラメンコ』 |
| 放送 | 2013年10月10日 -2014年3月27日 |
| 放送局 | フジテレビほか |
| 話数 | 全22話 |